「治験で死亡事故はあったの?」
「治験の副作用で後遺症が残ることはあるの?」
「治験の高額な報酬は危険度が高いから?」
治験に対して、このような印象や疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、過去に国内外で報告された死亡例や副作用リスクについて詳しく解説し、治験に対する誤解を解消することで、不安を抱える方が冷静かつ安心して判断できる材料をお届けします。
治験の安全性を支える仕組み
はじめに、治験に参加する方々の安全を守るために、どのような仕組みが整えられているのか、順を追ってみていきましょう。
なお、治験というと新薬のイメージが強いですが、それだけではありません。例えば、以下のような薬も治験を実施する必要があります。
- ジェネリック医薬品:既に処方・販売されている薬と同じ成分で作られたもの。一般的に「治験バイト」と呼ばれることの多い入院タイプの治験の多くが、これに該当します。
- 海外で承認済みの薬:日本では未承認だが、海外ではすでに使用されている薬。
厳格な基準と規制
大前提として、治験は参加者の安全を最優先に実施され、以下の国際基準や国内規制に基づき、治験の透明性と安全性が厳しく管理されています。
- ヘルシンキ宣言
世界医師会が採択した国際的な倫理基準で、参加者の人権と安全が最優先されます。 - GCP(医薬品臨床試験の実施基準)
厚生労働省が定めた国内基準で、治験の計画・実施・データ管理が科学的かつ倫理的に行われることを保証します。 - 治験審査委員会(IRB)
治験の計画が倫理的・科学的に妥当であるか、副作用リスクが適切に管理されているかを審査します。
リスクを最小限にする取り組み
治験では、副作用リスクを最小限にするため、薬の投与量は少量から始め、段階的に調整するなどの工夫がされます。
また、通常の診療よりも通院や検査の頻度が高く、専門医による丁寧な健康管理が行われます。これにより、体調の変化があれば早期に発見し、迅速に対応できる体制が整っています。
さらに、新薬の開発には9〜17年という長い期間と約500億円もの費用がかかるため、副作用による健康被害は、治験に参加される方々だけでなく、製薬企業にとっても極めて大きなリスクとなります。そのため、治験は非常に慎重かつ安全に実施されています。

私たちの健康へメリットをもたらす医薬品や医療機器、健康食品や化粧品などの有効性・安全性を検証するため、被験者を集めて日々「臨床試験」が行われています。臨床試験のうち国(厚生労働省)の承認を得るために行う臨床試験を「治験」といいます。 ここでは治験とは具体的に何なのか、より詳細かつ分かりやすく解...
インフォームド・コンセント
治験に参加する前には、期待される効果や起こり得る副作用、その発生確率などについて詳しい説明が行われます。
この説明は「インフォームド・コンセント(同意説明)」と呼ばれ、治験参加者が内容を十分理解したうえで参加を決定できる仕組みとなっています。
治験を途中でやめたいと思ったら
治験は、あなた自身の自由意思で参加するものであり、その意思は最大限に尊重されます。そのため、治験への参加は、開始前でも途中でも、いつでも辞退することが可能です。
万一、治験を途中で辞退した場合でも、それまでの参加日数や負担に応じて謝礼が支払われるケースが一般的です。
ただし、以下の点にはご注意ください。
- 規則違反や悪質な行為の場合
治験中に規則を破ったり、不適切な行動を取った結果、治験が中止や脱落となった場合には、謝礼が支払われないことがあります。 - 治験全体への影響
辞退が突然であった場合、参加者数が不足して治験そのものが中止となる可能性があります。その場合、他の参加者や治験全体に影響を与えてしまうことも考えられます。治験への参加を検討する際は、こうした影響についても理解したうえで、慎重に判断してください。 - 薬の服用後の辞退
すでに治験薬の服用が始まった場合は、安全性確認のため、辞退後も一定期間、経過観察のために通院が必要となる場合があります。
治験は新薬の開発に欠かせない重要なプロセスであり、多くの方の協力が不可欠です。ご自身の健康や状況を最優先しつつも、治験の重要性や他の参加者への影響を考慮して、適切な判断をお願いします。
治験の副作用
副作用という言葉を聞くと、つい危険なものを想像しがちですが、その程度はさまざまです。
治験に限った話ではなく、薬である以上、副作用は少なからず起こり得ます。
例えば、副作用として挙げられるものには以下のような症状があります。
万が一の場合でも適切な補償がある
万一、治験中に副作用が発生した場合でも、治験実施施設には医師や看護師が常駐しており、速やかに検査や治療を受けることができます。
さらに、製薬企業や治験実施医療機関に過失がなくとも、治験が原因で参加者に健康被害などの不利益が生じた場合には、以下のような補償が提供されます。
- 医療費:治験による健康被害の治療にかかる自己負担分を補填。
- 医療手当:通院の交通費や入院中の雑費などの費用を補填。
- 補償金:死亡や重度の障害が発生した場合に支給。
補償は医薬品副作用被害救済制度に準じて支払われます。詳細は、治験薬に係わる賠償責任保険のご案内をご覧ください。
ただし、参加者自身の故意や注意義務違反による健康被害は補償の対象外となるため、注意が必要です。
入院の治験で起こった死亡事故
上述したように、治験は厳格な基準と徹底した安全管理のもとで実施されており、そのリスクは非常に低いとされています。
しかし、稀なケースではありますが、過去には以下のような死亡例も報告されています。
日本で発生した治験の死亡事故
2019年7月、エーザイ株式会社が開発したてんかん治療薬の治験に参加した20代の男性が、電柱から飛び降りて死亡する事故が発生しました。
この薬と類似する薬には「自殺企図」の副作用が確認されており、厚生労働省が治験との因果関係を否定できないと判断したため、健康成人を対象とした新薬治験(フェーズ1)では日本初の死亡例として報告されました。
・事故の経緯
しかし、退院当日に自主的に再来院し、幻覚や幻聴、不眠を訴えました。
医療機関側は、受け答えが明瞭で容態が安定していると判断し、経過観察を続ける方針を選択しましたが、翌朝、男性が電柱から飛び降り、脳挫傷により命を落としました。
フランスで発生した治験の死亡事故
2016年1月、フランスで実施された新薬治験(フェーズ1)中に、パーキンソン病由来の気分障害や疼痛に対する治療薬を投与された被験者6名に重篤な神経系合併症が発生し、そのうち1名が死亡するというショッキングな事故が発生しました。
この治験は、動物実験の段階では特に問題が確認されていませんでしたが、健康な成人を対象とした臨床試験で深刻な被害が発生しました。
治験薬の安全性が問われる結果となり、世界的にも注目を集めたこの事故は、現在も詳細な情報の多くがフランス当局により開示されておらず、多くが謎に包まれています。
イギリスで発生した治験の事故
死亡事故ではありませんが、2006年3月、イギリスの新薬治験(フェーズ1)で「TG1412」という抗体医薬により発生した事故は、英国製薬史上最悪の治験事故とされています。
この治験では、健康なボランティア被験者8人のうち、実薬を投与された6名がサイトカインストーム(免疫暴走)を起こしました。
投与直後に多臓器不全に陥り、全員が集中治療室に搬送される事態となりました。
その後、全員が退院に至ったものの、1名は壊死によって手指を切断するという深刻な後遺症が残りました。
米国、カナダ、ドイツ、フランスで発生した治験の死亡事故
最後にご紹介する事例は、健康成人を対象とした治験ではありませんが、難病患者を対象とした治験中に発生したものです。
2021年9月9日、アステラス製薬は遺伝子治療薬「AT132」を用いた臨床試験で4例目の死亡事故が発生したと発表しました。
この治験は筋力低下が進行する難病「先天性ミオパチー」の5歳未満の患者を対象に、米国、カナダ、ドイツ、フランスで実施され、これまでに24人が投与されています。
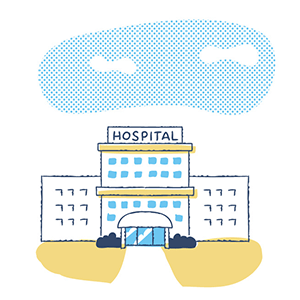
過去に高用量で3人が死亡したため、FDA(米食品医薬品局)は一時的に治験中断を指示しましたが、2020年12月に低用量で再開されました。
今回死亡した患者は再開後に唯一投与を受けた被験者で、死因は現在調査中とされています。
再発を受け、FDAは治験中断を再び指示し、アステラスは規制当局との協議を進めています。
データで見る治験の危険性とリスク
上記のような事例を見ると、「やっぱり治験って危険なんだ」と思われてしまうかもしれませんが、そうではありません。
治験のリスクを完全にゼロにすることはできませんが、それは治験だけではなく、私たちの日常生活にも当てはまります。
例えば、普段何気なく飲んでいる「かぜ薬」もその一例です。
一般用医薬品の副作用リスク
厚生労働省のデータによると、平成19~23年度の5年間における一般用医薬品(処方箋なしで購入できる薬)の副作用症例は1,220件に上り、そのうち死亡例は24件(副作用に占める死亡率は約2%)、後遺症が残った例は15件にのぼります。
その中でも、死亡例の半数(12件)は、私たちが日常的に使用する「かぜ薬(総合感冒剤)」によるものでした。
- 一般用医薬品の副作用症例:1,220件
- 死亡例:24件(約2%)
- 風邪薬による死亡例:12件(50%)
これらのデータを単純に治験のリスクと比較することはできませんが、もし治験で同様の事故が発生したら世間を大きく騒がせるニュースになるでしょう。
その背景にあるのは、市販薬が日常生活の一部として受け入れられている一方、治験はその言葉が持つ未知のイメージや「危険な人体実験」といった先入観や話題性があるためです。
高額な報酬が出るのは危険だから?
「治験の報酬が高額なのは、危険だからでは?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。
しかし、実際には治験の報酬が高額になる理由は、長時間の拘束と行動制限による負担にあります。
たとえば、入院タイプの治験では、報酬の相場は1泊あたり15,000~30,000円程度です。
金額だけを見ると高額に感じられますが、治験参加中は24時間拘束され、以下のような制限が課されます:
- 外出や面会ができない
- 決まった時間に診察や検査がある
- 入院中の食事は完食しなければならない
- 治験内容により入浴(シャワー)不可の日がある
これらの制限は、治験薬の効果を正確に評価するために必要なものです。このような負担を考慮すれば、たとえ1泊で20,000円の謝礼金が支払われるとしても(1時間あたり約833円)、不自然ではないことがイメージできるのではないでしょうか。
なお、治験で支払われる報酬や謝礼金は「負担軽減費」と呼ばれます。詳しく知りたい方は、下記のリンクをご覧ください。

治験は、新しい薬や治療法の開発を支える重要なボランティア活動ですが、一般的なボランティアとは異なり、「報酬」が得られる点もその大きな魅力のひとつとなっています。 治験の報酬は、正式には「負担軽減費」と呼ばれ、参加者が負担する時間的・経済的負担を軽減する目的で支払われます。これは、労働の対価とし...
治験に参加する意義
治験は「危険」「副作用が多い」といったイメージが先行しがちですが、その多くはデータに基づかない先入観によるものです。
一方で、治験の意義についてもぜひ考えてみてください。私たちが普段何気なく使用している薬は、すべて治験というプロセスを経て開発されています。
こうしている今も、世界中で多くの方が治験に協力し、日本でも年間数万人以上の方が治験に参加しています。そして、その結果として生まれた薬やワクチンが、これまでにどれだけ多くの命を救ってきたかは言うまでもありません。

例えば、現在広く使用されている抗生物質や血圧降下薬、さらには新型コロナウイルスのワクチンも、治験を経て初めて私たちの元に届きました。治験への協力は、医療の進歩に欠かせない貢献であり、未来の命を救うことにつながります。
ぜひ、皆さんには過去に起こってしまった事例を踏まえた上で、治験への参加がもたらす良い面にも目を向けてほしいと思います。
近い将来、治験が「危険なバイト」という偏ったイメージではなく、献血のように広く認知され、命を支えるためのボランティア活動として多くの方に認知されることを願っています。
ぺいるーとでは、治験に参加された方の体験談を掲載しています。治験参加についての生の声を聞きたい方は、引き続きこちらもご覧ください。

「治験の報酬は魅力的だけど、実際に参加した人はどう感じたんだろう?」 このような不安を抱える方は少なくありません。治験について詳しく知らないと、「後遺症や副作用のリスクがあるこそ、高額な報酬が設定されているのでは?」と考えがちです。 さらに、ネット上には不安を煽る記事や動画も多く見られるため、余...
副作用に関する面白い雑学
治験における副作用をより深く理解していただくため、本章ではそのポジティブな側面についてご紹介します。
「治験中に副作用が発覚した」と聞くと、危険なイメージを持ちやすいかもしれません。しかし、副作用とは必ずしもネガティブなものではありません。副作用が新たな主作用として応用され、画期的な薬の誕生につながることもあるのです。
まず、主作用と副作用の違いを整理してみましょう。
- 主作用:その薬に期待する本来の効果
- 副作用:薬に期待する効果以外の働き
例えば、現在広く使用されている発毛剤や睡眠改善薬、さらにはED治療薬も、副作用がきっかけで誕生した薬の一例です。
発毛剤は副作用から生まれた薬
発毛剤の代表例である「ミノキシジル」は、もともと高血圧症治療剤として使用されていました。米国企業が販売した高血圧症治療薬「ロニテン」に、多毛・発毛という副作用が確認されたことが発端です。
副作用の調査を進めた結果、血圧を下げる成分「ミノキシジル」に発毛効果があることが判明しました。これを受け、1988年にミノキシジルを主成分とした発毛剤が開発され、現在では「リアップ」などの製品として広く使用されています。
睡眠改善薬やED治療薬も副作用がきっかけ
副作用が新たな薬の主作用として応用された事例は他にもあります。
- 睡眠改善薬
アレルギー症状を緩和する薬「ジフェンヒドラミン」には、服用後に眠気を催す副作用がありました。この作用を利用して誕生したのが、市販されている睡眠改善薬「ドリエル」です。 - ED治療薬
ED治療薬として有名な「バイアグラ」も、副作用をきっかけに誕生した薬です。もともと狭心症の治療薬として開発されましたが、期待した効果が乏しかったため、治験参加者が薬を返却しない理由を調べたところ、男性機能の改善が確認されました。これがバイアグラ開発の出発点です。
副作用が新たな発見を生む
ある状況では副作用とみなされる作用が、別の状況では主作用として役立つ場合があります。
このように副作用が新薬の開発や既存薬の改良につながるケースは決して珍しくありません。
副作用は「危険」というイメージだけでは語りきれない側面があり、医療の進歩において重要な発見の一端を担っているのです。
治験が不安な初心者におすすめの治験とは?
薬は、大きく分けて新薬(先発医薬品)とジェネリック医薬品(後発医薬品)の2種類に分類されます。
| 医薬品の区分 | 概要 |
| 新薬(先発医薬品) | 従来にはない薬効成分を持つ、新たに開発された医薬品 |
| ジェネリック医薬品(後発医薬品) | 特許期間を終えた新薬と同じ成分で作られた医薬品 |
ジェネリック医薬品は、すでに処方・販売されている薬と同じ成分でつくられており、元となる新薬は特許期間中(実質15年程度)に多くの人々に使用されてきた実績があります。そのため、「すでに安全性が確認されている薬」といえます。
新薬の治験が必ずしも危険というわけではありませんが、初めて治験に参加する方にとって、ジェネリック医薬品の治験は、より安心して参加しやすい選択肢ではないでしょうか。ただし、ジェネリック医薬品も私たちが普段飲んでいるお薬と同様に100%副作用がないというわけではありません。
なぜジェネリック医薬品は治験をするの?
ジェネリック医薬品は、元となる薬と同じ成分で作られているため、治験の必要性に疑問を持つ方もいるかもしれません。
実際には、効能や用法用量は元の薬と変わらないものの、形状や色、添加物に変更が加えられる場合があります。このため、体内での吸収や排泄に違いが生じる可能性があり、それを検証するために治験が必要です。
治験では、既存の薬とジェネリック医薬品を比較し、血中濃度の推移に統計学的な差がないかを確認します。この試験を「生物学的同等性(BE)試験」と呼びます。日本で実施される健康成人を対象とした入院治験の過半数は、この試験に該当します。
ジェネリック医薬品の治験に参加してみたいと思われた方は、以下の記事で入院治験の流れや合格するためのコツをぜひご覧ください。

入院の治験に参加する際、事前の健康診断に合格するためのコツや合格率は、誰もが気になるところです。 この記事では、健康診断に合格するためのポイントや、治験参加までの流れ、入院中のスケジュールについて詳しく解説します。初心者の方でもわかりやすいよう、入院の治験の全体像を余すことなく網羅しました。 ...
まとめ
「治験薬だから副作用がある」「危険だから謝礼金が高額である」——こうした意見は、治験の本質を十分に理解しないまま抱かれた先入観に基づくものです。ここまでお読みいただいた方には、世間の治験に対する評価が必ずしも公平ではないことを、少しでもご理解いただけたのではないでしょうか。
治験に対して過度な不安を抱く方もいますが、国内の事例を見ても実際の死亡率や副作用発生率は極めて低いことが統計で示されています。
とはいえ、初めて治験への参加を検討する方にとって、不安が残るのは自然なことです。
そんなときは、まず説明を聞いてみることをおすすめします。治験では、参加前に期待される効果や副作用の内容、その発生確率について、詳細な説明が行われます。「インフォームド・コンセント」と呼ばれるこのプロセスを通じて、理解を深め、納得した上で参加を判断することができます。
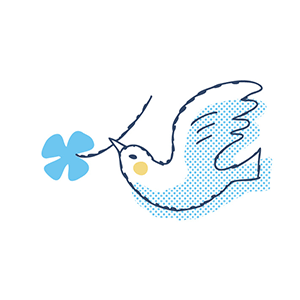
現状、日本では治験の参加者が不足しており、それが国内の薬の開発を遅らせたり、薬価の高騰につながる要因ともなっています。「説明を聞いて納得できなければ辞退すればいい」という気軽なスタンスで、治験について前向きに考えていただければ幸いです。
治験は命を救う薬の開発に欠かせない重要なプロセスです。その役割を正しく理解し、治験への参加をポジティブに検討いただけることを心から願っています。






















